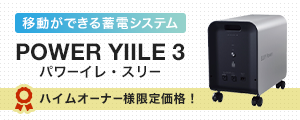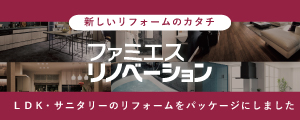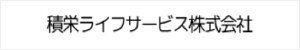日々の生活の中で害虫駆除に苦慮されている方も多いのではないでしょうか?
今回はコールセンターへお問い合わせの多い害虫駆除、対策の一例をご紹介させて頂きます。
アリ駆除のポイント

- アリの進入口を見つける
(アリが一番多くいる場所、窓枠、ドアの隙間等を確認してみる) - 家の中のアリを退治
(数匹の場合はテッシュでふき取り。数が多い時はウエットテッシュや床用洗剤を染み込ませた雑巾などでふき取る) - 巣を駆除する
(巣の上から殺虫剤を散布したり、巣の周辺に毒餌やアリ用のジェル剤を置いてみる) - 侵入経路をふさぐ
(家の中のアリと巣の駆除が済んだら、アリが入ってくる入口部分にパウダータイプの殺虫剤などをかけ、進入口をふさぎます。侵入経路が分からない場合は、窓枠、ドアの角に殺虫剤をまいて下さい。)
参考1:巣が見つからない場合
アリに毒餌を持ち帰らせて、巣ごと駆除する方法があります。
毒餌殺虫剤をアリの行列ができている所や、アリの見られる所に配置します。建物の内部に巣を作っていて巣穴が見つからない場合、アリが出入りしている壁の隙間、割れ目などに殺虫剤を噴射してみて下さい。
参考2:身近なもので応急対処例
- 重曹と粉砂糖を混ぜたものを、アリの巣近くに置いてみる。
- 食器洗い洗剤と水を1:2の割合で薄めたものを吹き付けてみる。
- お酢を入れた水で、アリ道の拭き掃除をしてみる。
※家具、床材等の塗装の変色に注意して下さい! - ハッカ油、ミント水を雑巾に少量含ませて、アリの通り道を拭いてみる。
※ハッカ油は猫などのペットがいる場合には、使用しないで下さい!
ハチの駆除について

基本、専門業者へ依頼をして頂くことをお勧めしています。
防護服を貸し出してくれる市町村もあるようですが、ハチの種類、巣の大きさや場所などにより、注意しなければならない事がたくさんあります。判断を誤れば命に係わることなので、個人での勝手な判断はしないで頂くように、ご注意下さい。
参考1:ハチの巣の近くで作業する場合の注意点
- 日中、ハチの活動が活発な時間はなるべく避ける。
- 整髪料や香水など臭いをつけない。
(個人差がありますが、汗の臭いにも反応する場合があります) - 黒などの濃い色の服は着ずに、白に近い色を選ぶ。
- 長袖を着たり首にタオルを巻くなど、肌の露出を極力減らす。
参考2:予防対策
- 3~4月頃がお勧め。
- ハチ用の忌避剤や殺虫剤を、巣を作りそうな場所にまいておく。
- 巣を作り始める前に水をかける。
- 木酢液を水で薄めてからスプレーで吹き付けたり、バケツなどに入れて置いても効果があります。
コウモリの駆除について

コウモリは「家から追い出す」という、手法で行わなければなりません。
コウモリ用の駆除剤も市販で販売されていますが、コウモリを追い出す事に成功しても、駆除剤の効果があるうちに出入口を速やかにふさぐ作業をしなければ、また同じ隙間からコウモリが入ってきてしまいます。
意外と時間がかかる調査や駆除の為、専門業者に依頼することをお勧めします。
ヤスデの駆除について
ヤスデは人を咬むことはなく、土壌を肥沃にしてくれる益虫です。
しかし見た目や大量発生することから害虫と呼ばれています。
特に発生しやすいのは梅雨の時期である5月~7月と、雨の多い9月~11月です。
家の周りに大量発生した場合は忌避剤がおすすめ
- スプレータイプ 壁にも使用できる
- パウダータイプ 家を囲むように散布できる(防水効果をご確認ください)
- 置くだけタイプ 非常に簡単で、小さく目立たない
家に侵入した場合は殺虫剤や凍殺スプレーで駆除
- 殺虫剤(ムカデ・ヤスデに効果があるものを選んでください)
- 凍殺スプレー お子様やペットがいるご家庭でも安心
予防方法
- 家の周りの落ち葉や雑草の掃除
- 庭や家の周りの水はけを改善し、ヤスデが地上に出てこない環境にしましょう