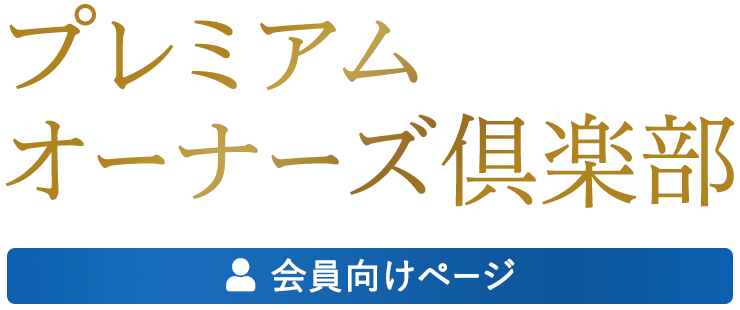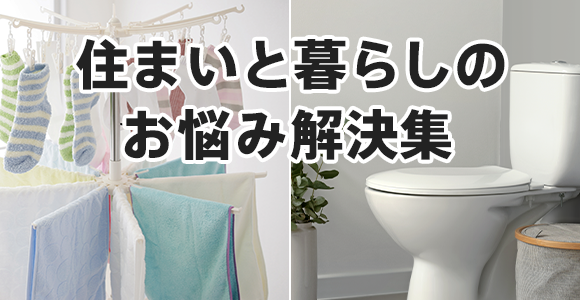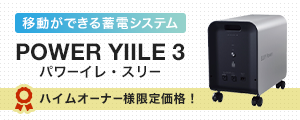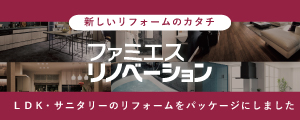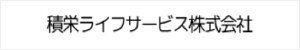このページではプレミアムオーナーズ倶楽部会員様向けのコンテンツを掲載しています。
ここに掲載されている内容は毎月2回配信しているメールマガジンでもご覧いただけます。
プレゼント当選者発表
-

ヤクルトVS.巨人戦観戦チケットプレゼント
【臨時号】プレミアムオーナーズ倶楽部メルマガプレゼント当選者2025年6月24日 -

宮崎県産合挽き肉のチーズ入り生ハンバーグ
【2025年6月1号】プレミアムオーナーズ倶楽部メルマガプレゼント当選者2025年6月20日 -

高所ラクラクおそうじセット
プレミアムオーナーズ倶楽部 2025年度 春の新規入会キャンペーン当選者2025年6月10日
暮らしのお役立ちコラム
メールアドレス変更/メルマガ配信停止
「お問い合わせフォーム」よりメールアドレスの変更/メルマガ配信停止のお手続きが可能です。
ご相談内容の「プレミアムオーナーズ倶楽部のメールアドレスを変更」または「プレミアムオーナーズ倶楽部メールマガジンの停止」にチェックのうえ、必要事項を入力して送信してください。
プレミアムオーナーズ倶楽部に関する
お問い合わせ先はこちら
お問い合わせ先はこちら